R/Cカーはただのおもちゃではなく、複雑な機械です。
その大きさからは想像も出来ないパワーを受け止めて高い性能を発揮し続けるためには、メンテナンスが欠かせません。
ここでは、故障になる前にトラブルの元を発見する方法や、メンテナンスのポイントなどをご紹介します。
一番熱いのはどれ?
R/Cカーの走行において、発熱は避けられません。
しかし同時に、熱によってモーターもバッテリーもアンプも性能低下や劣化を起こし、故障の原因になることもあります。
あらかじめこれらのエクイップの内どこに大きな負担がかかっているかをチェックして対策を施しておくことで、トラブルを回避できる可能性があります。
特にこれらのエクイップの内どれか一つでも『触っていられないほど熱くなっている』ようだと、下のような対策が必要だと考えればいいでしょう。
極端に発熱が
大きい(共通) | RCカーのどこにせよ、触れないほど熱くなるというのはどこか異常です。
下のような場合、どこかの発熱が大きいと考えられます。発熱がどこに出るかというのは、それぞれ状況によって違ってきますが、まずこれをチェックしましょう。
- ギア比が高すぎる:
ギア比が高すぎる(ピニオンギアが大きすぎる/スパーギアが小さすぎる)と、駆動系の負担が増えます。ギア比を下げて走行させましょう。
- ギアやプーリー、ベルトが痛んでいる:
ギアの歯かけやベルトの劣化・飛びによって駆動系に負担がかかることがあります。
この場合、走行音が異常に大きくなることが多いです。傷んでいる部品をチェックして新品に交換しましょう。
- 急加速をくり返している:
RCカーを走行させていて、いちばん駆動系に負担がかかるのが「急加速」です。これをくり返すと各部の発熱が大きくなるのは当然です。
スロットル操作を丁寧に行うよう心がけましょう、その方がタイムも縮むはずです。また、他に対策としては、ギア比を下げるのも有効です。 |
|---|
| モーターが熱い |
- モーター(コミュテータ)のコンディションが悪い:
コミュテータ(下の『モーターのメンテナンス』の項の図参照)のコンディションが悪いと、そこで火花が散って発熱の原因となります。同時に電波ノイズの原因にもなるので、コミュテータのコンディションには注意しましょう。
『モーターのメンテナンス』の項で紹介する「再慣らし」などを行ってみてください。
540モーター・スポーツチューン以外のモーターなら、市販のコミュテータクリーナーでメンテナンスできる他、少々高価になりますがコミュ研磨機でメンテナンスすることもできます。
- バックやブレーキを多用している:
これも上と同じように、コミュテータから火花が散って発熱の原因となります。
特に現在のRC用モーターは540モーターなどごく一部を除いて『進角』がついています。進角付きのモーターを逆回転させてバックさせると、特に強い火花が発生して発熱の原因になります。
|
|---|
バッテリーが
熱い |
通常の発熱の範囲であれば、バッテリーが一番熱くなるというのは理想的な状態だといえます。
ただし触っていられないほど発熱するとなると、異常です。上の共通ポイントに追加して、以下のポイントをチェックしましょう。
- ショートしている:
配線のどこか(おそらくバッテリー→アンプ間)、もしくはバッテリーの被覆が破れた部分からショートしている可能性があります。
特にバラセル状態でカーボンシャシーを使っているような場合に、セルの端子が直接カーボンシャシーに触れているとショートします。
場所に関わらず、ショートは致命的なトラブルの原因になります。徹底したチェックをしましょう。
- セルが死んでいる:
表示されている容量よりも極端に少ない容量しか充電できない場合や、いくつかあるセルの内1個だけが極端に発熱している場合、バッテリーが劣化してしまっていることが考えられます。
新しいバッテリーを購入するしかないようです。
|
|---|
| アンプが熱い |
- アンプの容量が小さい:
廉価版アンプでは流せる電流に限界があります。また、使用している部品も低価格のものが多く、高級アンプに比べれば内部の電気抵抗が大きい分発熱も大きいのが普通です。
例えばアンプの説明書に『20Tまで使用可能』と書かれていたとしても、高いギア比を組んでいれば23Tモーターでもそのアンプの能力を超えた電流が流れてしまいます。(『オーバーヒート』の項で詳説)
この場合は、上級クラスのアンプに買い換えるのがお薦めの対策です。ギア比を下げることでも一時的には回避することができますが、応急処置に過ぎません。
- アンプの故障・劣化:
アンプに使用されている電子部品は、RCカーの走行ではかなり酷使されている状態です。
特に廉価版アンプでは劣化も早く、故障やトラブルも起こりがちです。
アンプが劣化や故障の場合はメーカーに修理を依頼するしかありません。『オーバーヒート』の項で詳説しますが、頻繁にヒートプロテクトが作動するような場合は、上級アンプに買い換えるのがいいでしょう。
|
|---|
| どれもほとんど熱を持っていない | これは基本的には問題ありません。しかし手持ちのエクイップメントの性能を十分に引き出しているとは言えない状態ではあります。
この状態での走行に慣れたら、もう少しギア比を高くして走行してみるのも楽しいと思います。 |
|---|
モーターのメンテナンス
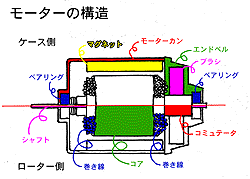
ブラシレスモーターは基本的にメンテナンスフリーですので、ここでは従来のブラシ付きモーターに関してのみ記述します。あらかじめご了承下さい。
モーターのメンテナンスの解説をする前に、右のモーター用語がどの部分を指しているかを示した図を見てください。
540モーターとは外観は相当違っていますが、構造も用語も同じです。
RCカーを走らせている間、モーターには非常に大きな負担がかかっています。
走行後のメンテナンスを行わないと、あっという間に性能低下を起こし、使えなくなってしまうのです。
また、新品のモーターに対しても、コミュテータ部分のアタリをとるために同様の「慣らし」を行います。
新品に対して行う場合も、走行後に行う場合も「慣らし」の方法自体は同じです。
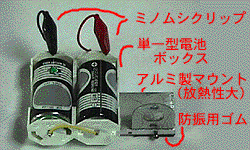
専用の「モーター慣らし器」も市販されていますが、左のようなモノを作って単一乾電池で「慣らし」をする方法もあります。
要するに、「無負荷・低電圧」でモーターを発熱させないように回転させればいいのです。
この時、モーターのコミュテータ部に、「モータークリーナー」として市販されているケミカル材を何度か少量ずつスプレーします。これはブラシが摩耗してできるカーボンスラッジをコミュテータに付着させないためです。
回転し始めはコミュテータ部から小さな火花が散っているはずです。

コミュテータの表面がピカピカになり、この火花が見えなくなるまで回します。モーターが発熱してきたら、途中で止めて冷めるまで待ちます。
面倒くさいと感じるかも知れませんが、これをやるとやらないではモーターのパワーも寿命も段違いです。
もう一つ、モーターのメンテナンスというか、使用法で注意しなければならないのが、「発熱」です。
RCカーの走行後(バッテリー1本、思うように走行した後)、モーターが触れないほど熱くなっているようだと問題です。
モーターに使われている永久磁石は熱によって劣化し、磁力が衰えてしまいます。
具体的にはモーターのトルクがガタ落ちしてしまうのです。
ギア比を下げ(ビニオンギアを小さくするか、スパーギアを大きくする)て、モーターの負荷を減らしてやりましょう。
バッテリーのメンテナンス
この項も、基本的にメンテナンスフリーが売り物の新しいバッテリー、LiPoとLiFeについては触れません。あくまでもニッカドとニッケル水素に関する項目だと考えてお読み下さい。
『RCカーを選ぶ』の放電器の項で解説したとおり、R/Cカーの走行用バッテリーには放電は欠かせません。
ところがこの放電がやっかいで、放電させすぎてもいけないのです。
パックされている6個のセルには個体差があります。すべてのセルをめいっぱい放電しようとすると
『転極』という現象が起こり、パックまるごとダメになってしまうのです。転極について詳しく知りたい方は
こちらをご覧ください。
また、ニッケル水素電池は、電気を完全にカラにしてしまうのはよくないと言われています。
これらの状態をまとめて『過放電』とも呼びます。
個体差が少ないように組み合わされたマッチドバッテリーであっても転極や過放電は起こり得ます。
これらの現象を防ぐために、中クラス以上の放電器ではオートカット機能が付いているのです。
シャシーのチェック
走行後、たとえ大きなクラッシュがなくてもシャシーのチェック箇所がいくつかあるので、紹介しておきます。
| チェック箇所 | チェック項目 |
|---|
| デフギア | デフギアは特に新しい部品を組み立てた直後の走行後には動作が悪くなることがあります。
左右のタイヤを逆方向に回転させて、ゴリゴリとかコツコツとかいう引っ掛かり感のある抵抗を感じたら、メンテナンスしましょう。 |
| シャシー裏面 | シャシー裏面があまりに傷だらけになるようだと、その場所で走らせるには車高が低すぎる可能性があります。要チェックです。 |
| サスペンション | クラッシュをした場合、サスシャフトが曲がるなどしてサスペンションの動きが悪くなっていることがあります。
またダンパーの組み立てが悪いとダンパー内に気泡が混入することがあります。 |
| 駆動用ギア周辺 | ギアに埃や砂粒などが挟まっていると、かみ合っているギアも含めて部品をダメにしてしまいます。よくチェックして、古い歯ブラシやつまようじを使って取り除いておきましょう。 |
ボディの補修

ボディの補修には、グラスネット入りのアルミテープ(右画像の右端)かシューグー(右画像の中央)とグラスネット(右画像の左端・シューグーに付属)を使用します。
例はかなりひどく破損してしまったボディを、グラスネットとシューグーを使用して補修しています。このくらい割れていてもなんとか使えるようになりますので、このテクニックをおぼえるとボディはかなり長持ちするようになります。
 |
作業前のボディです。フロント部分を中心にバキバキに割れてしまっています。
|
 |
まずボディの表裏両方についているゴミや埃を拭き取ります。
RCカー用クリーナーを使用する場合は、塗料やボディ自体を溶かしてしまう製品もありますので、まず目立たないところでテストしてから使用してください。
作例のボディは塗装の際に黒で裏打ちしてあるため、ボディ裏面は真っ黒です。
ボディの弱い部分には補強のために最初からグラスネットを張ってありましたが、度重なるハードクラッシュのため、その補強のフチを回り込むように割れが発生してしまいました。 |
 |
割れてしまったボディを元の状態に仮止めします。
ボディ塗装の時に使ったマスキングテープを使用し、ボディ表面から固定します。
接着力の強いテープを使うと、剥がす際にステッカーを一緒に剥がしてしまうことがあるのでマスキングテープを使用します。 |
 |
ボディ裏側から適当な大きさに切ったグラスネットを貼り付けます。
グラスネットには弱い接着剤がついていますので弱くですがくっつくます。ネットの網目をズラしていくことでかなりきつい曲面にもなじませることが可能です。
ネットの向こうに見えている銀色のパーツは、ヘッドライト電飾の反射板です。電飾用の配線も見えます。 |
 |
シューグーを塗ります。
チューブから直接だと大盛りになってしまうので、ネットの中央部に盛り上げたあとへらで伸ばすようにしてネット全体がシューグーで固まるように塗ります。
シューグーは30分程度で表面が乾燥しはじめますが、塗りつける厚さによって乾燥時間はことなります。筆者の場合は一晩おいて完全に乾燥させてからボディ表面のマスキングテープを剥がすようにしています。 |
シューグーの類似製品の中には塗料を溶かしてしまうものがあります。ご注意下さい。
ボディ製作の際、弱い部分にあらかじめグラスネットとシューグーをつけておくことで補強することもできます。
この場合、もちろん補強は塗装後に行います。
作例では強度を重視してシューグーとグラスネットを使っていますが、グラスネット入りアルミテープを使用すればもっと手軽に補修可能です。
タイヤのチェック

走行後よく見られるのが、タイヤの剥がれです。
右のような状態になるとタイヤグリップも安定せず、とても走らせにくくなります。
新品タイヤを貼るのと同じ要領で、瞬間接着剤で補修しましょう。

クラッシュするとホイルが割れることがあります。
高速回転しているホイルには、軽いクラッシュでも想像以上に力が加わっているようで、意外なほど簡単にひびがはいっていることがあるので要注意です。
ひびくらいなら一時しのぎとしては瞬間接着剤で補修することも可能ですが、やはりセッティングは微妙に変わってしまいますし、しょせん一時しのぎなので強度的にも弱くなります。
また完全に割れてしまった場合は交換するしかありません。
ボールデフのメンテナンス
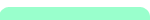

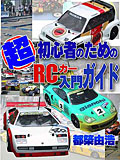


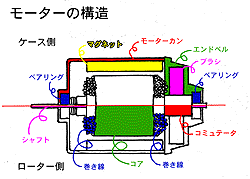 ブラシレスモーターは基本的にメンテナンスフリーですので、ここでは従来のブラシ付きモーターに関してのみ記述します。あらかじめご了承下さい。
ブラシレスモーターは基本的にメンテナンスフリーですので、ここでは従来のブラシ付きモーターに関してのみ記述します。あらかじめご了承下さい。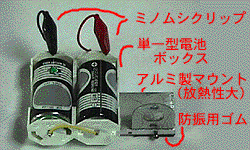 専用の「モーター慣らし器」も市販されていますが、左のようなモノを作って単一乾電池で「慣らし」をする方法もあります。
専用の「モーター慣らし器」も市販されていますが、左のようなモノを作って単一乾電池で「慣らし」をする方法もあります。 コミュテータの表面がピカピカになり、この火花が見えなくなるまで回します。モーターが発熱してきたら、途中で止めて冷めるまで待ちます。
コミュテータの表面がピカピカになり、この火花が見えなくなるまで回します。モーターが発熱してきたら、途中で止めて冷めるまで待ちます。 ボディの補修には、グラスネット入りのアルミテープ(右画像の右端)かシューグー(右画像の中央)とグラスネット(右画像の左端・シューグーに付属)を使用します。
ボディの補修には、グラスネット入りのアルミテープ(右画像の右端)かシューグー(右画像の中央)とグラスネット(右画像の左端・シューグーに付属)を使用します。




 走行後よく見られるのが、タイヤの剥がれです。
走行後よく見られるのが、タイヤの剥がれです。 クラッシュするとホイルが割れることがあります。
クラッシュするとホイルが割れることがあります。